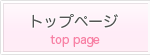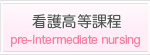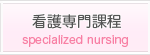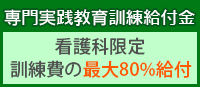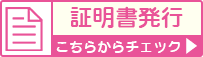『合理的配慮を必要とする学生の支援』制度について
合理的配慮について
学生のみなさんには学ぶ権利があります。
本来、学び方にはさまざまな方法がありますが、多くの人は提示された方法や環境に適応しながら学んでいます。
しかし、心身の機能等に何らかの制限や特性がある場合、多くの人が何気なく適応している方法や環境ではうまく学べない状況が生じることがあります。
このような場合、学習するうえで障壁となる設備・手段・ルールに対しては、“合理的配慮”を求めることができます。
このことは、障害者権利条約・障害者差別解消法でも認められている権利です。
申請者(支援を必要とする学生)と本校とが建設的対話を通して配慮内容を決定します。
決定された配慮内容を学生及び保証人が合意のもと、学科担当が講師・実習施設の承認を得ることにより、支援の提供を行います。
対象となる学生
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により断続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生(慢性疾患、難病その他の機能障害等も含みます)。
合理的配慮に含まれない可能性が高い事柄
ある支援の内容が合理的配慮の範囲に含まれるかどうかは、一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じて検討されなくてはなりません。
そのため、申請者と本校との建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。
ただし、下記の事柄は、上に示した合理的配慮の意味するところに照らして、合理的配慮に含まれない可能性が高いと考えられます。
- 看護師・准看護師育成のための教育目的・内容に関わる本質的な変更を伴うこと
- 公平な成績評価の保障を損なう基準の引き下げや卒業要件の緩和
- 本校の現状に照らして、体制面、財政面において均衡を失した、又は本校と申請者以外の学生にとって過度の負担を課すもの
- 本校の本来的業務に帰属あるいは付随しないもの
合理的配慮申請の流れ
合理的配慮の検討および実施は学生本人と本校が主体となり行います。
以下の流れで申請とヒアリングを行いながら、合理的配慮の内容を決定していきます。
なお、合理的配慮はどのタイミングでも申請ができますが、事後での対応は難しいため、何らかの困難が想定される場合は事前にご相談ください。
- 合理的配慮申請書および添付書類を、申請者本人が所属している課程の教務主任へ提出します。
合理的配慮申請書ダウンロード(PDF)
合理的配慮申請書ダウンロード(EXCEL)▼
- 合理的配慮申請書および添付書類の内容をもとに、『申請の内容・現状・支援を希望する事項』についてヒアリングを行います。ヒアリング内容をもとに支援計画書を作成します。
▼
- 支援委員会で申請内容及び支援計画書を確認し、配慮可能な支援を決定します。その後、申請者本人及び保証人へ決定事項を伝達いたします。学生本人及び保証人の決定事項に対する合意の意思確認を行います。
※障害の状態や状況が変わる、あるいは、求めた配慮が有効に機能しない場合など、必要に応じて再検討を行います。また、添付資料(診断書、障碍者手帳等)の追加提出を求める場合があります。▼
- 「支援計画書」にもとづいて支援の提供を開始します。
※支援の内容については年1~2回程度、学生及び保証人との面談を通し、必要に応じて見直しを行います。
※手続きには最低3週間程かかります。学生本人より話を聞き、十分な審議や検討が必要となりますので、時間に余裕を持ってご相談くださいますようお願いいたします。
令和7年4月1日